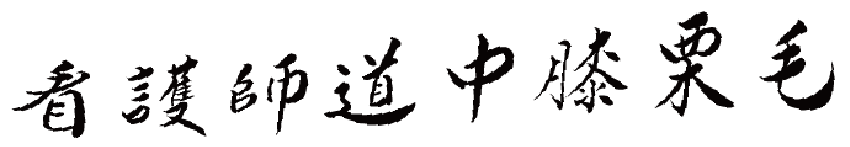最近、娘の成長発達が著しく、日々新たな発見があり嬉しい気持ちになる一方で、何だか寂しい気持ちにもなっている僕です。
我が子に思いを馳せていたら、ぐるぐると頭が回って考えることがあったので、綴ってみます。
期待に応えていく娘
娘を見ていて思うこと。
それは、両親や周りの親戚の期待に必死に答えようとしているように見えること。
私たち両親は、それぞれの親や周りの人達からの子育ての期待に応えようとしています。
そして、その期待を背負う両親の期待を受けて、色々なことが結果的には早く出来るようになっていく娘。
これ、ちょっと過去の自分に当てはまるような気がしているんです。
周りの期待に応え続けていた自分
1. 期待される、とは?
僕は、昔から家族をはじめ、周りの人達からの期待に応えて生きてきたように思います。
厳密にいうと、この「期待」は、「こうなってほしい!」というニュアンスは家族からしか受けていなくて、大半の周りの人達からのニュアンスは「あなたはこういう人だよね!、こうなるんだろうな」という『イメージ像』です。
僕はこの周りからの『イメージ像』に、たくさんの成長をさせてもらい、同時に呪いのようにつきまとい、苦しんできました。
2. 期待=イメージ像との闘い
初めに強調しておきますが、僕の家はいわゆる「お勉強」重視の家庭では全くありませんでした。
むしろ勉強しなさいと言われたのって、人生で2回?あるかないかです。
(そのせいで追い込まれる時以外は一切勉強しない性格になってしまいましたが)。
さて、僕にとっての「期待」との闘いは、幼少期から始まっていました。
自分で言うのは恐れ多いですが、僕が過ごした地域において、僕は幼少期から成績は良い方で育ちました。
好奇心が旺盛で、周りにあるもの、その原理が何でも知りたかった。
たくさん周りの人に聞いたり調べたりして、分かることがとても嬉しかったのです。
振り返ってみると、何かが分かって覚えられた僕を、周りの大人はたくさん褒めてくれました。
それが嬉しくて、僕はどんどん学ぶことが楽しくなります。
いつしか、周りの期待=イメージ、「あなたは〇〇も出来る」といった、呪縛とも取れるようなイメージに、僕は囚われていきます。
小学校2年のとき、国語で75点を初めて取ったときがありました。
(でも小学校の国語って、1問10点とか15点の問題もあるので、よく考えたら普通にあること笑)
でも、答案を持って帰った時、祖母にとても悲しまれた?(当時の僕はそう感じた)出来事があったのです。
うちの祖母は今になって思うと、そんなに勉強を重視するような人でもないので、よく考えたら自分の勝手な受け取り方だったと思うのですが、これをきっかけに、僕はその後一切それを下回る点数を取りたくない一心に駆られました。
暗示のように「自分は常に良い点数を取るんだ」と言い聞かせている(そんなつもりなんて全く無かったのだが)自分が、もうそこには完成していたのです。
周りの期待に応えるということ② へつづく